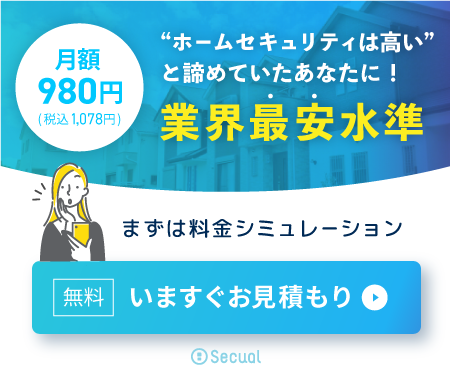敬老の日は「親を思う日」
9月の第三月曜日は「敬老の日」。
長寿を祝い、感謝を伝える日として親しまれていますが、同時に「遠くに住む親の暮らし」に思いを馳せる方も多いのではないでしょうか。
電話やビデオ通話で元気な声を聞ければ安心できます。
しかし、実際には一日の生活リズムや体調のちょっとした変化までは分かりません。
親が高齢になればなるほど、離れて暮らす家族にとって「ちゃんと元気にしているだろうか」という不安は大きくなります。
そんな背景から、近年注目されているのが「ホームセキュリティを利用した見守り」です。
防犯だけでなく、“暮らしの安全”を支える仕組みとして進化しているのです。
なぜ“見守り”が必要なのか
高齢化が進む日本では、65歳以上の一人暮らし世帯は年々増加しています。
総務省の統計によれば、65歳以上の高齢者のうち、ひとり暮らしは約700万人以上。
今やどの家庭にとっても「高齢の親の見守り」は現実的な課題となっています。
問題は「自宅の中で起きるリスク」です。
転倒や体調不良、熱中症などは外出先だけでなく、家の中でも起こります。
特に夏や冬は体調変化が起こりやすく、急に意識を失ったり、動けなくなったりするケースもあります。
「昨日も電話したから大丈夫」と思っていたのに、実はその後に異変が起きていた――そんな不安を払拭できる手段が必要です。
ホームセキュリティの新しい役割
ホームセキュリティというと、「空き巣や不審者を防ぐ」イメージが強いかもしれません。しかし最近はその役割が広がりつつあります。
窓やドアの開閉、人の動きを検知するセンサー類は、防犯用途にとどまらず「家の中の生活リズムを見守る」ツールとしても活用できます。
つまり、親の安否確認を“センサーが自動で行う”という発想です。
従来の見守りサービスはカメラを用いることが多く、プライバシーの問題から敬遠される方もいました。
その点、ホームセキュリティのセンサーなら「必要な動きだけを検知」するため、監視されているような感覚を与えず、自然な形で見守りが可能になります。
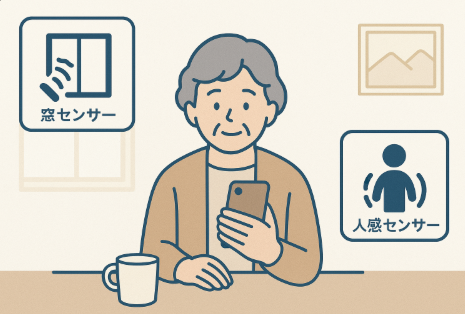
見守りに使える具体的な機能
では、ホームセキュリティの見守り機能にはどのようなものがあるのでしょうか。
窓センサー
窓やドアの開閉を検知するセンサー。
防犯用途では「侵入者が窓をこじ開けたとき」にアラートが鳴りますが、見守り用途では「一定期間、玄関の開閉がない」といった異変を察知できます。
例えば、外出の習慣があるのに何日も玄関の開閉がない場合、「体調不良で動けないのでは」と早期に気づけるのです。
人感センサー
赤外線などで人の動きを感知するセンサー。
居間やキッチンなど生活の中心となる場所に設置することで、日常的な行動を把握できます。
普段は朝に必ずキッチンで動きがあるのに、その日は反応がない――そんな異常を家族に知らせることが可能です。
通知機能
センサーの反応は、スマートフォンへリアルタイムで通知できます。
単に「鳴る」だけではなく、「動きが一定時間検知されていない」「窓の開閉が数日間なかった」など、異常の可能性を家族に知らせる仕組みです。
カスタマイズ性
「1日間動きがなければ通知」といったように、家庭の生活リズムに合わせて設定できます。
これにより「親らしい生活パターン」と「異常」を見分けやすくなります。
実際のシナリオ
朝の動きが検知されない
普段は午前7時にキッチンで人感センサーが反応するのに、その日は動きがない。
電話をしてみると「体調が悪くて起き上がれなかった」と分かり、早めに対応できた。
夜中のドア開閉を検知
深夜2時、玄関のドアが開いた通知が届く。
認知症の兆候がある親が外へ出ようとしていた。家族が気づいて声をかけられた。
外出が長期間ない
毎日散歩に出かけていた親が、3日間一度も外出していない。
センサー通知で気づき、電話すると「転んで足を痛めた」と判明。すぐに病院へ連れて行けた。
これらは「センサーがあったからこそ早期に気づけた」事例です。
家族と高齢者、双方にやさしい仕組み
センサーによる見守りは、家族と高齢者双方にメリットがあります。
家族の安心
「連絡がない=無事」と思い込まずに済む。
センサーが代わりに日常をチェックしてくれるため、精神的な安心感が大きい。
高齢者のプライバシー保護
カメラのように常時映されるわけではないので「監視されている」という圧迫感がない。
自分の暮らしを尊重されながら、さりげなく見守られる。
自然に続けられる仕組み
特別な操作や手間は不要。
センサーは自動的に働き、必要な時だけ家族に通知するため、生活に負担をかけない。
まとめ:敬老の日に「安心」を贈る
敬老の日は、感謝の気持ちとともに「これからも安心して暮らしてほしい」という願いを伝える日でもあります。
離れて暮らす親の安全を守る手段として、ホームセキュリティの見守り機能はとても有効です。

センサーによる安否確認は、家族の安心だけでなく、高齢者自身の暮らしの質を守ることにもつながります。
今年の敬老の日には、感謝の言葉に加えて「安心の仕組み」を贈ってみてはいかがでしょうか。