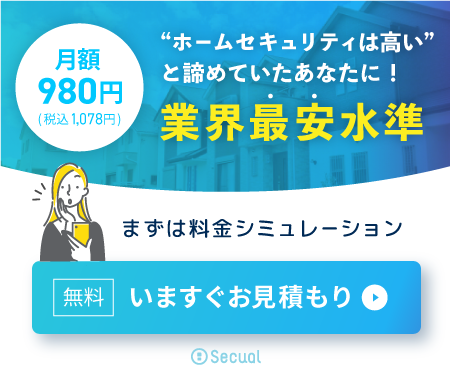はじめに
近年、宅配業者を装った詐欺が全国で増加しています。
コロナ禍を経てECサイトの利用が一般化し、多くの家庭で宅配便を受け取る機会が増えました。
その状況を悪用し、偽の宅配業者が個人情報を盗んだり、家に侵入しようとするケースが発生しています。
本記事では、宅配詐欺の実例を紹介しながら、本物と偽物を見分ける方法と具体的な防犯対策を解説します。
実際に起きた宅配詐欺の事例
事例1:偽の不在通知で個人情報を盗む手口
東京都内のマンションで、不在時に「宅配便の不在通知」がポストに投函されていた。
しかし、その通知には通常の宅配業者のロゴはなく、記載されていた電話番号に連絡すると、「再配達のために個人情報を確認したい」と不自然な要求をされた。
被害者が警戒して調査したところ、その電話番号は宅配業者とは無関係のものだった。
▶ ポイント
- 不在通知の発行元が不明瞭な場合は注意。
- 公式サイトや正規アプリで問い合わせ先を確認する。
事例2:宅配業者を装い玄関を開けさせる手口
大阪府で発生した事件では、犯人が大手宅配業者の制服を着てインターホンを鳴らし、荷物の配達を装った。
ドアを開けた瞬間に押し入り、金品を強奪するという強盗事件が発生。
実際には、事前の配送通知などはなく、住人が不審に思って警察に通報したことで被害は未然に防がれた。
▶ ポイント
- 事前に注文した覚えがない荷物には警戒。
- 宅配員の身分証を確認する。
事例3:宅配業者を名乗るフィッシング詐欺
最近増えているのが、SMS(ショートメッセージ)での詐欺。
「お荷物の配達に関するお知らせ」との文面でURLが送られ、クリックすると偽サイトに誘導される。
そこでログイン情報やクレジットカード情報を盗まれる被害が急増。

▶ ポイント
- SMSのリンクは安易に開かず、公式アプリや正規サイトで確認。
- 不審なURLはアクセスせず、すぐに削除する。
- 本物と偽物を見分けるポイント
見分け方のポイントについて
ここでは本物と偽物を見分ける際のポイントをいくつかご紹介します。
1. 不在通知の差出人を確認
本物の宅配業者の不在通知には、以下が記載されています。
- 正式な会社ロゴ
- 正しい電話番号
- 正規の再配達受付用URL(QRコードやアプリ経由)
偽物の不在通知には、
- 会社名が曖昧(例:「配送センター」など)
- 連絡先が個人の携帯番号やフリーダイヤルではない番号
- QRコードやURLが不自然(公式サイトと異なる)
といった特徴があります。
2. 宅配員の身分証を確認する
正規の宅配業者は、基本的に身分証明書を携帯しています。
配達時に不審な点があれば、「身分証を見せてください」と確認してみてください。
本物の宅配業者
- 制服やロゴ入りのジャンパーを着用
- 身分証明書を提示できる
- 正規の送り状が荷物に貼付されている
偽物の宅配業者
- 制服やロゴがない、または不自然
- 身分証の提示を拒む
- 送り状に違和感がある(手書き、文字がぼやけているなど)
3. 事前に荷物の有無を確認する
突然の配達には要注意。ECサイトで購入履歴を確認し、以下をチェックしてください。
- その日に届く荷物があるか
- 公式アプリの追跡情報と一致しているか
宅配詐欺を防ぐための対策
1. スマートインターホンを活用する
カメラ付きインターホンを設置し、宅配業者を名乗る人物を確認する。
不審な場合はインターホン越しに対応し、直接対面しない。
2. 宅配ボックスを活用する
対面での受け取りを減らし、宅配ボックスやコンビニ受け取りを利用することで、不審者との接触を避けられる。
3. SNSでの個人情報管理を徹底する
自宅の住所や受け取り予定の荷物に関する情報をSNSに投稿しない。
特に「〇〇を注文した!」などの投稿は、詐欺の標的になる可能性がある。
💗 女性の防犯 安心Navi 💗 その投稿、本当に今じゃないとダメ? 今日の安心ポイント 写真は時間や数に気を付けて安心💗 誰に見られてもいいことだけにして安心💗 投稿は家に帰ってからが[…]
4. 公式アプリやサイトで配送状況をチェック
宅配業者の公式アプリやECサイトで、配送状況をリアルタイムで確認する。
SMSで届いたリンクを直接開くのではなく、必ず公式アプリから確認する。
5. 不審な場合は警察に通報
不審な宅配業者が来た場合や、不在通知の内容が怪しい場合は、警察(#110)や自治体の防犯相談窓口へ通報する。
まとめ
宅配便を装った詐欺は年々巧妙化していますが、本物と偽物を見分けるポイントを理解し、適切な対策を取ることで被害を防ぐことができます。
「不審な宅配はまず疑う」、「公式情報を確認する」、「直接対面せず慎重に対応する」 という基本的な防犯意識を持ち、安全な宅配受け取りを心がけましょう。